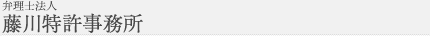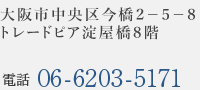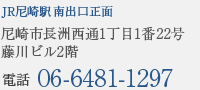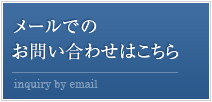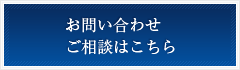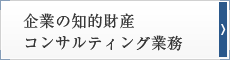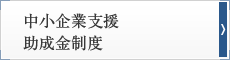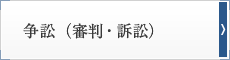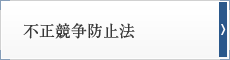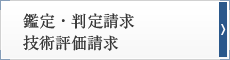【知財情報】知財高裁令和3年(行ケ)第10052号のご紹介
「カット手法を分析する方法」が、人間の精神活動に該当すると認定された事例
第1 事案
ヘアカット手法を分析する方法が、特許法上の「発明」であるかが争われました。
第2 概要
1.本件発明の請求項1
【請求項1】
分析対象者の写真、画像、イラストまたはデッサンから、正面、側面および背面から観た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを推定する第1のステップ、
次いで、分析対象セクションを複数のセクションの中から選択する第2のステップ、
次いで、第2のステップで選択したセクションに対して、第1のステップで推定した自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルに基づき
A アウトラインの形状または表情分析
B カットライン分析
C ボリューム位置またはボリュームライン分析
D シルエット形状または表情分析
E パート(分け目)の位置または有無分析
F セクションの幅または形状分析
G フェイスラインとセクション間の継がり方またはセクション間の継がり方分析
の中から、前記選択されたセクションに適した少なくとも1つの分析項目の分析を行い、分析結果を得る第3のステップ、
次いで、前記分析結果から、前記カット手法に関する情報を導出する第4のステップによる、
前記選択されたセクションに対して採用されているカット手法分析方法。
2.裁判所の判断
裁判所は、(1)特許法上の「発明」とは何かを示し、(2)本件発明がこれに該当しないとを判断しました。
(1)特許法上の「発明」
裁判所は、まず、以下のように特許法上の発明とは何かを示しました。
| ・・・特許の対象となる「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であり(同法2条1項),一定の技術的課題の設定,その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである。 そうすると,請求項に記載された特許を受けようとする発明が,同法2条1項に規定する「発明」といえるか否かは,前提とする技術的課題,その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし,全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かによって判断すべきものである。 そして,上記のとおり,「発明」が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることからすれば,単なる人の精神活動,意思決定,抽象的な概念や人為的な取り決めは自然法則とはいえず,また,自然法則を利用するものでもないから,直ちには「自然法則を利用した」とものとはいうことはできない。 したがって,請求項に記載された特許を受けようとする発明に何らかの技術的手段が提示されているとしても,その技術的意義に照らして全体として考察した結果,その課題解決に当たって,専ら,人の精神活動,意思決定,抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体に向けられ,「自然法則を利用した」ものといえない場合には,同法2条1項の「発明」に該当するとはいえない。 |
まとめると、設定された技術的課題を解決したのが人の精神活動,意思決定,抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体と評価できれば、特許法上の発明に該当しない、ということを示しました。
(2)本件発明は特許法上の「発明」に該当するか
裁判所は、次に、本件発明が特許法上の「発明」に該当するかについて検討しました。以下のとおり、本件発明は「自然法則を利用したものであるとはいえない」、すなわち特許法上の「発明」には該当しないとされています。
| 本願補正発明は,こうした第1のステップないし第4のステップを順次経ることにより,特定のセクションに採用されているカット手法を分析する方法であり,本願補正発明の発明特定事項には,分析の主体が特定されていないことから,人がこうした分析を行うことは排除されていない。 そうすると,本願補正発明には,人である分析者が,分析対象者の正面,側面及び背面の写真を見て,分析者の毛髪の知識や経験を踏まえて,自然乾燥ヘアスタイルを分析者の頭の中で推定することを発明特定事項に含20 むものであり,こうした推定を含む第1のステップは,仮に,分析者の頭の中で行う分析の過程で利用する毛髪の知識や経験に自然法則が含まれているとしても,分析者の頭の中で完結するステップである以上,分析者の精神的活動そのものであって,自然法則を利用したものであるとはいえない。 |
第3 検討
(1)特許法上にいう「発明」に該当するには、その発明が1.技術的思想の創作であって、2.自然法則を利用するもので、3.高度なもの、であることが必要です(特許法第2条1項1号)。
また、2.自然法則を利用しないものとして、a.人間の頭の中だけの考え(精神活動)、b.学問上の原理(数学の公式など)、c.人為的な取り決め(つまり、人間が勝手に決めたルール。例えば法律・規則・ゲームのルール)があります。
(2)本願発明は「人間の精神活動」そのものであるから、「自然法則を利用」しないものである、したがって特許法上の発明ではない、というのが裁判所の判断です。
(3)本願では、コンピュータを介さず、課題解決はすべて分析者(人間)の判断・思考に委ねられています。そのため、特許法上の発明に該当しないとして特許になりませんでした。
なお、本願のような「人間の精神活動」が特許法上の発明ではない(特許権を付与されない)とされる理由は、次のように説明できます。
まず、特許法の法目的は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」(特許法1条)です。すなわち、新しい特許技術を公開した者には特許権を付与し,第三者は公開された発明を利用する機会を与えることにより、産業の発達に寄与する必要があります。
ところが、その発明が「人間の精神活動」にすぎなければ、すなわち、人の頭の中で考えた方法に過ぎなければ、第三者にとって客観的に再現可能なものとは言えません。そうすると、特許法の法目的を果たすことができません。
このような理由により、「人間の精神活動」にすぎないものは、特許法上の発明とは認められない、というわけです。
(文責:三上祐子)