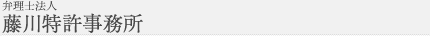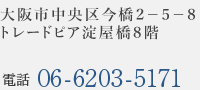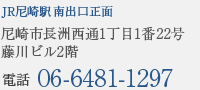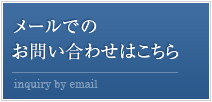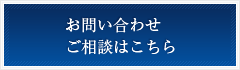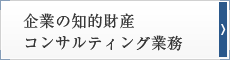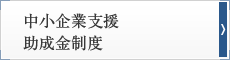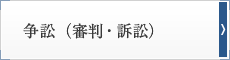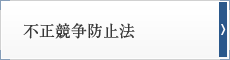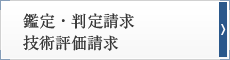【知財情報】知財高裁令和5年(ネ)第10040号のご紹介
審美目的の施術が医療行為に該当しない等と認定された事例
第1 事案
美容クリニックを経営する控訴人(第1審被告、医師)が、当該クリニックにおいて豊胸術に使用するための組成物を製造し、被施術者に投与したとして、特許侵害が問題となった事案です。
特許法では、医薬の発明、医療機器の発明は特許権の対象となるのに対し、医療行為の発明(人間を手術、治療又は診断する方法の発明)は特許権の対象となりません。これは、「医療行為では緊急の対応が求められる場合があるので、医師が、特許侵害を懸念しながら医療行為を行う必要があるような状況は好ましくない」という理由によります。また、医薬の発明は特許権の対象となるものの、医師等による調剤行為には特許権の効力が及ばないこととしています。
本事案では、医師である控訴人が、上記の例外的な枠組みを根拠に非侵害を主張したが、裁判所はこれを認めなかった、という事案です。
第2 概要
1.本件特許発明の請求項1(特許第5186050号)
【請求項1】
自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有してなることを特徴とする皮下組織増加促進用組成物。
2.裁判所の判断
裁判所は、控訴人の以下の主張をいずれも退け、特許侵害が成立すると判断しました。
(1)本件特許発明は実質的に医療行為への特許であるから無効理由があるという主張
(2)本件実施は調剤行為であるから特許権の効力が及ばないという主張
(1)本件特許発明は実質的に医療行為への特許であるから無効理由があるという主張
本件特許発明である「組成物」は、まず被施術者から「自己由来の血漿」を採取し、それを含有する「組成物」を当該被施術者に投与することを前提としています。
控訴人は、このような「組成物」の使用のされ方に着目すると医療行為に密接に関連しており、実質的には本件特許発明は「医療行為の発明」であるため、特許法上の無効理由があるとの主張をしました。
医療行為が特許の対象外とされる理由
医療に関する発明には、医療機器、医薬品、治療方法(医療行為)などがあります。このうち、医療機器や医薬品は現在では特許の対象となっていますが、医療行為は特許権の対象外とされています。
その理由は主に人道的な観点によるものです。つまり、「医療行為では緊急の対応が求められる場合があるので、医師が、特許侵害を懸念しながら医療行為を行う必要があるような状況は好ましくない」という理由によります。。
具体的には、特許法では「産業上利用することができない発明」は特許を受けられないと規定されており、特許・実用新案審査基準ではその典型例として「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」が挙げられています。
| (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 |
| 第 1 章 発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第 29 条第 1 項柱書) 3.1 産業上の利用可能性の要件を満たさない発明の類型 以下の(i)から(iii)までのいずれかに該当する発明は、産業上の利用可能性の 要件を満たさない。 (i) 人間を手術、治療又は診断する方法の発明(3.1.1 参照) |
したがって、本件特許発明が医療行為に該当するものであれば、本来特許されるべきではなかったといえますが、裁判所はこの主張を明確に退けました。
| 昭和50年の特許法改正により、医薬の発明が特許を受けられることが明確にされたことからすると、人体に投与することが予定されていることをもっては、その「物の発明」が実質的に医療行為を対象とした「方法の発明」であるとして、「産業上利用することができる発明」に当たらないと解釈することは困難である。 |
| 人間から採取したものを原材料として、最終的にそれがその人間の体内に戻されることが予定されている物の発明について、そのことをもって、これを実質的に「方法の発明」に当たるとか、一連の行為としてみると医療行為であるから「産業上利用することができる発明」に当たらないなどということはできない。 |
(2)本件実施は調剤行為であるから特許権の効力が及ばないという主張
控訴人は医師であり、被施術者から採血して本件特許発明に係る組成物を製造した行為は、特許法69条3項の規定により特許権の効力が及ばないと主張しました。
特許法69条3項とは
この規定は、調剤行為に特許権が及ぶ事態を回避するために設けられたものです。医師等による調剤は処方箋に基づくものであり、患者の健康回復という社会的使命を伴うことから、特許権の効力を及ぼさないとするのが当然と考えられています。
| (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。 |
したがって、本件実施が上記に該当する「二以上の医薬を混合して製造される医薬の発明」であれば、特許権の効力は及ばないといえます。
しかし、裁判所はこの主張も退けました。
| 本件特許発明に係る組成物は、明細書等の記載からして、豊胸のために使用するものであり、その目的は主として審美にあるとされている。その上、現在の社会通念に照らしてみても、本件特許発明に係る組成物は、「人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物」と認めることはできない |
第3 検討
現行の特許法では医薬に関する発明も特許の対象となっていますが、特許法が制定された昭和34年当時は、医薬は特許を受けられませんでした。
その理由は、戦後の日本では医薬の開発技術が未成熟であり、医薬特許を認めると欧米企業が日本市場を独占するおそれがあるため、国内産業の保護を目的としていたと考えられます。
その後、日本の技術力の向上に伴い、昭和50年の法改正で医薬に関する発明が特許の対象とされました。
ただし、医師等が安心して医療行為を行えるように、同時に第69条が設けられ、医療行為に特許権の効力が及ばないことが明確にされました。
今回の事案で、控訴人の行為が「医療行為」と認められなかったのは、それが「審美目的」であり、「人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物」ではなかったためです。
第69条は、医薬発明に特許権を認めるという原則に対し、例外的に効力を制限する規定です。したがって、その適用範囲を不必要に広げるべきではありません。
この点で、本判決の判断は妥当といえます。
もっとも、「病気の治療」と「審美目的の施術」との境界は必ずしも明確ではありません。
たとえば、事故で顔に傷を負った場合、救命のための手術は明らかに「治療」に該当しますが、その後、手術跡を目立たなくするための施術は「治療」といえるのか、それとも「審美目的」とみるべきなのか、という問題があります。
このような場合、心情的には後者も「治療」として扱われることを望みたくなります。
(文責:三上祐子)