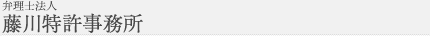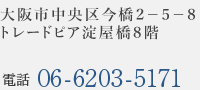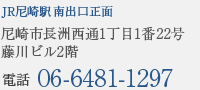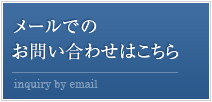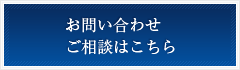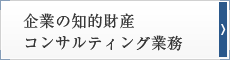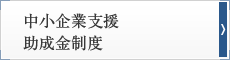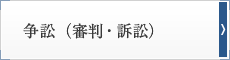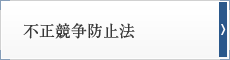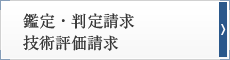【知財情報】知財高裁令和5年(行ケ)第10059号のご紹介
独自の薬の処方方法が、人間の精神活動、人為的取決めに関わる発明と認定された事例
第1 事案
薬の処方箋の作成において、患者が保有していると思われる前回受診時の薬の残量も勘案し、処方する量を決定する方法が、特許法上の「発明」であるかが争われました。
第2 概要
1.本件発明の請求項1
【請求項1】
再診時、医薬品を処方、処方箋作成時、処方箋には、以前の受診予約日前受診・処方により患者の手元に残った医薬品(以下、患者保有の医薬品と記載する。)のうち、今回処方した期間で服用できずに残る医薬品で、0日分も含めた患者保有分(以下、患者保有分と記載する。)項目を設け、前回、処方した医薬品で分量・用法・用量(投与日数を除く)も同じ場合、今回の投与日数の算定は、
二つのパターン
パターン1
前回、処方した医薬品が受診予約日の前日で残数が発生しない場合
パターン2
前回、処方した医薬品が受診予約日の前日まで患者保有分が残っている場合
に区分し、
パターン1では
イ 受診予約日での受診では
受診日(前回の受診予約日)から受診予約日(新たな受診予約日)の前日まで
ロ 受診予約日前での受診では
a 新たな受診予約日が前回の処方箋作成時の受診予約日より後(同日含まず)では、前回の受診予約日から新たな受診予約日の前日まで
b 新たな受診予約日が前回の処方箋作成時の受診予約日と「同日」では、患者保有分「0日」で、期間は投与日数最終日(受診予約日の前日)
c 新たな受診予約日が前回の処方箋作成時の受診予約日より前(同日含まず)では、患者保有分は前回の受診予約日の前日から遡って受診予約日まで
パターン2では
イ 受診予約日での受診
a 新たな受診予約日が患者保有分を生起させた直前の処方箋作成時の受診予約日より、後(同日含まず)では、患者保有分を生起させた直前の受診予約日から新たな受診予約日の前日まで
b 新たな受診予約日が患者保有分を生起させた直前の処方箋作成時の受診予約日と同日では、患者保有分0日、期間は投与日数最終日(受診予約日の前日)
c 新たな受診予約日が患者保有分を生起させた直前の処方箋作成時の受診予約日より、前(同日含まず)では、患者保有分は患者保有分を生起させた直前の受診予約日の前日から遡って受診予約日まで
ロ 受診予約日前での受診
a 新たな受診予約日が患者保有分を生起させた直前の処方箋作成時の受診予約日より、後(同日含まず)では、患者保有分を生起させた直前の受診予約日から新たな受診予約日の前日まで
b 新たな受診予約日が患者保有分を生起させた直前の処方箋作成時の受診予約日と同日では、患者保有分0日、期間は投与日数最終日(受診予約日の前日)
c 新たな受診予約日が患者保有分を生起させた直前の処方箋作成時の受診予約日より、前(同日含まず)では、患者保有分は患者保有分を生起させた直前の受診予約日の前日から遡って受診予約日まで
として、投与日数に患者保有分項目を設けた処方箋と患者保有の医薬品を含めた医薬品投与日数算定を特徴とする方法。
2.裁判所の判断
裁判所は、(1)特許法上の「発明」の意義を明示し、(2)本件発明がこれに該当しない、と判断しました。
(1)特許法上の「発明」の意義
| 特許の対象となる「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であるから(特許法2条1項)、人の精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決めなどは、「自然法則を利用した」ものといえず、特許の対象となる「発明」に該当しない。 そして、特許請求の範囲(請求項)に記載された「特許を受けようとする発明」が特許法2条1項にいう「発明」に該当するか否かは、それが、特許請求の範囲の記載や願書に添付した明細書の記載及び図面に開示された「特許を受けようとする発明」が前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当するか否かによって判断すべきものである。 |
(2)検討
| 本願発明は・・・処方箋に「患者保有分」の項目、すなわち患者が保有している医薬品に関して記載する項目を設け、既に患者が保有している医薬品に相当する分を除いた投与期間を算定する方法の発明であって、これによって、重複処方を防止する効果が得られるとされるものである。 しかしながら、本願発明のうち、「処方箋」の記載事項は、医師法施行規則21条で規定されているから、「分量、用法、用量」の記載は法令に基づく規定、すなわち人為的な取決めと解され、したがって、「分量、用法、用量」として記載される「投与日数」も人為的な取決めであり、本願発明において、処方箋に「投与日数」として「患者保有分」の項目を設けることもまた、処方箋に医師が記載する事項を定めた人為的な取決めにすぎず、自然法則を利用したものであるとはいえない。 また、本願発明は、患者が保有している医薬品に相当する分を除いた投与期間を算定する方法として、パターン1及びパターン2に分け、さらにパターン1についてイ、ロa・b・c、パターン2についてイa・b・c、ロa・b・cにそれぞれ分けて、算定方法を具体化しているが、いずれの算定方法も、医師が患者に対して医薬品を処方し、投与する際の投与期間の算定の方法を定めた人為的取決めであって、自然法則を利用したものであるとはいえない。 以上によれば、本願発明は、全体として人為的な取決めであって、自然法則を利用したものとはいえないから、特許法2条1項にいう「発明」には該当しない。 |
第3 検討
(1)特許法上にいう「発明」に該当するには、その発明が1.技術的思想の創作であって、2.自然法則を利用するもので、3.高度なもの、であることが必要です(特許法第2条1項1号)。
また、2.自然法則を利用しないものとして、a.人間の頭の中だけの考え(精神活動)、b.学問上の原理(数学の公式など)、c.人為的な取り決め(つまり、人間が勝手に決めたルール。例えば法律・規則・ゲームのルール)があります。
(2)本願発明は「人為的な取り決め」に該当するから、「自然法則を利用」しないものである、というのが裁判所の判断です。より詳しくは、「(2)検討」において、以下のように判断し、全体として人為的な取り決めだとして、2.を満たさないと判断しました。
- 処方箋に何を書くか(「分量・用法・用量」など)は、医師法施行規則という法律で決まっている(法律は人為的な取り決めである。)
- 「投与期間をこうやって計算しよう(パターン1、2)」という手順も、医師の行動ルール(人為的な取り決め)を定めただけで、自然法則に関係していない。
(3)本願発明のような、自然法則を利用しないアイデアに特許を認めると、社会に大きな不都合が生じます。たとえば、病院内の書類の記載方法や、学校での出席管理の手順といった業務上のルールに特許が認められてしまうと、それを取り入れるたびに特許料を支払う必要が生じ、業務運営が不当に制限されてしまいます。これでは、「産業の発達に寄与する」という特許法の目的を阻害しそうです。
特許制度は、自然法則を応用した技術的な工夫に対して独占権を与えることで、産業の発展を促進する制度です。したがって、人為的な取り決めだけから成るアイデアには特許を認めるべきではなく、本件でもその原則に基づいて判断がなされたといえます。
(文責:三上祐子)