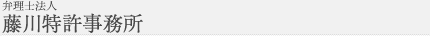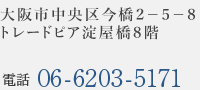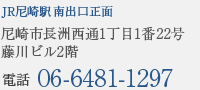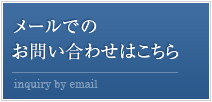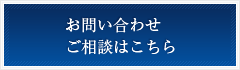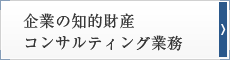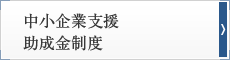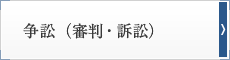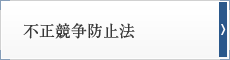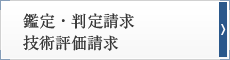【知財情報】知財高裁令和6年(行ケ)第10047号のご紹介
ゴジラの3D形状商標が商標法3条1項3号に該当するが、3条2項に該当すると認定された事例
第1 事案
今回の事案では、本願商標が商品の形状か、および、出願人(原告)のものとして著名となっているか、について争われました。
商標法においては、商標とは商品の出所を表すものという考え方があります。例えば、消費者が靴に付されたNIKEのロゴを見て「この靴はナイキのものだ」と認識します。このように、商品の出所を認識させるのが商標、という考え方があります。
そのため、商品の出所を表さないものは、商標ではないから、原則、登録できません。商品の出所を表さないものにはいくつかパターンがありますが、その一つが、商品の形状です。例えば、なんのロゴもついていない靴の形状だけを見ても、普通はその靴の出所はわかりません。
ただし、例外的に、商品の形状が商品の出所を表す場合があります。その商品の形状が、ある会社のものとして非常に有名な場合です。たとえば、クリスチャン・ルブタンのレッドソールは有名です。赤い靴底を見ただけで、ルブタンとわかります。
この事案では、本願商標が商品の形状であることは特許庁と裁判所で見解が一致しましたが、出願人(原告)のものとして著名となっているか、について、裁判所は特許庁とは異なる見解を示しました。
第2 概要
1.本願商標
【商標】
第10047号のご紹介_本願商標-300x297.png)
【指定商品】
第28類 縫いぐるみ,アクションフィギュア,その他のおもちゃ,人形
2.裁判所の判断
裁判所は、本願商標について以下のように判断しました。
(1)商標法3条1項3号に該当する(本願商標は商品の形状である)
(2)同条2項に該当する(本願商標は出願人のものとして著名となっている)
(1)商標法3条1項3号に該当する
裁判所は、まず、以下のように、商品の形状が商標登録を受けられない理由を示しました。
| ・・・商品の形状は、本来、商品の機能をより効果的に発揮させたり、美観を向上させるために選択されるものであるから、商品の形状からなる商標は、その形状が、需要者において、その機能又は美観上の理由から選択されると予測し得る範囲を超えたものである等の特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範囲を出るものでなく、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとして、商標法3条1項3号に該当するものと解される。 |
そして、本願商標が商標法第3条1項3号に該当するかについては、「本願の指定商品を取り扱う業界においては、恐竜や怪獣(恐竜等をモチーフにした想像上の動物)をかたどった立体的形状からなる様々な商品が製造、販売されている実情が存在する」ことを勘案し、本願商標は商品の形状と理解されるとし、同号に該当すると判断しました。
つまり、本願商標は、単に縫いぐるみ,アクションフィギュアの外観であって、見た目のかっこよさ(美観)という形状にすぎないから、(冒頭にたとえで示したなんのロゴもついていない靴のように)出所はわからないだろう、ということです。
(2)同条2項に該当する
商品の形状でも、長年の使用により出願人のものとして著名となっている場合は同条2項に該当し、登録が認められます。
ここで、「使用により出願人のものとして著名となっている」というためには、使用してきた商標が、出願に係る商標と同一であることが条件となっています。この点で、本願は他の一般的な事例にはない特殊性がありました。というのは、本願商標に表されたゴジラは、映画「シン・ゴジラ」に登場するゴジラであって、原告が昭和29年から長年使用しているゴジラとは同一視できないものだったのです。たとえば、以前のゴジラと比べ、シン・ゴジラは、頭が小さく、尾尻が太く長いです。
これについて、裁判所は以下のように述べています。
| シン・ゴジラの立体的形状は、それ以前のゴジラ・キャラクターと比較して、頭部が小さくなり、前脚(腕)の細さが一層際立つ一方、尻尾はより太く長くなっているなど、全体のプロポーションに違いが生じているほか、背中から尻尾にかけての部分を中心に赤みがった色彩が加わっている等の違いがあり、被告が主張するとおり、両者を同一(実質的に同一)と認めることは相当でない。 しかし、商標法3条2項の「使用」の直接の対象はシン・ゴジラの立体的形状に限られるとしても、その結果「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる」に至ったかどうかの判断に際して、「シン・ゴジラ」に連なる映画「ゴジラ」シリーズ全体が需要者の認識に及ぼす影響を考慮することは、何ら妨げられるものではなく、むしろ必要なことというべきである。 |
続いて、裁判所は、シン・ゴジラの形状が、「それ以前のゴジラ・キャラクターの基本的形状をほぼ踏襲している」として、さらに「当該基本的形状は、映画「シン・ゴジラ」の公開以前から、本願の指定商品の需要者である一般消費者において、原告の提供するキャラクターの形状として広く認識されていたことが優に認められる。」としました。すなわち、長年使用されているゴジラの基本的形状は消費者に広く認識されており、シン・ゴジラはその基本的形状をほぼ踏襲している、ということが認定されました。
上記の点、ならびその他の事項も勘案し、本願は同条2項に該当すると認定されました。
第3 検討
本件は、シン・ゴジラの著名性を検討するにあたり、以前のゴジラについての使用を考慮することが許されるかどうかについて判断した点が有意義であると思料いたします。
裁判所の判断は、「以前のゴジラの使用」=「シン・ゴジラの使用」ではないとしても、シン・ゴジラが著名となっているかについては、以前のゴジラの著名性が及ぼす影響は考慮されるべき、というものです。
特許庁商標審査基準においては、「出願人のものとして著名となっている」と主張するには、使用してきた商標と、出願に係る商標が同一であることが求められています。
すなわち、「これだけたくさん使用してきたから、私のものとして著名となっているはずです」ということを特許庁に分かってもらうために、たくさんの資料を特許庁に提出しますが、それら資料に掲載されている商標(使用してきた商標)は、出願に係る商標と同一であることが求められています。同基準では、この同一性は厳格な同一が求められています。どれくらい厳格かといいますと、縦書きが横書きになった程度では同一とみなされる一方、書体が変更されていた場合は同一とみなされません。
このように、厳格な同一性が求められるのが原則なため、特許庁では、「本願商標は出願人のものとして著名となっている」とは認められませんでした。一方、裁判所は同一ではないが出願にかかる商標の著名性に影響を与えている点に着目し、「本願商標は出願人のものとして著名となっている」と認めました。
本件の裁判所の判断を参考に、例えば「これまで使用してきた商標は、出願に係る商標と同一ではないが、出願人の商品に対する需要者の認知度を高めてきた」など、もともと注目度が高い商標であった等の事情が著名性を主張する根拠となり得るとも考えられる点は、今後の実務へ応用できそうだと感じます。
(文責:三上祐子)