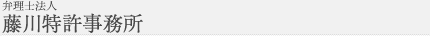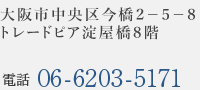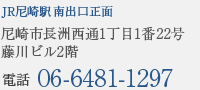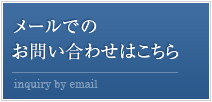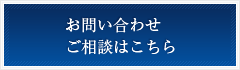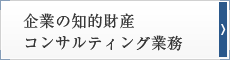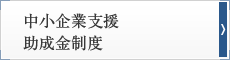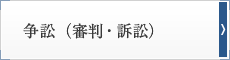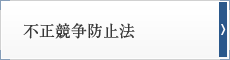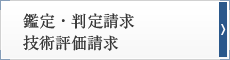【知財情報】ソフトウェア関連発明の裁判例(3)
「人脈関係登録システム事件」:「とき」とは
平成29(ネ)第10072号(知財高裁 平成30年1月25日判決言渡)
第1 争点(請求項中の文言の解釈)
特許権侵害の成否は、被疑侵害品が特許権の請求項に記載の構成要件を全て充足するかどうかにより判断される。そして、構成要件を充足するかの判断に際し、ある文言(用語)をどのように解釈すべきか、がポイントとなる場合がある。
本件は、下記の本件特許権1の「送信したとき」という文言の解釈が、争点となった事例である。
第2 概要
1.本件特許権1(特許第3987097号)
【請求項1】
登録者の端末と通信ネットワークを介して接続したサーバであって、
人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージと人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージとを交換した登録者同士の個人情報を記憶している記憶手段と、
第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを第一の登録者の端末(以下、「第一の端末」という)から受信して第二の登録者の端末(以下、「第二の端末」という)に送信すると共に、第二の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末に送信する手段と、
上記第二のメッセージを送信したとき、上記第一の登録者の個人情報と第二の登録者の個人情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段と、
上記第二の登録者の個人情報を含む検索キーワードを上記第一の端末から受信する手段と、
上記受信した第二の登録者の個人情報と関連付けて記憶されている第二の登録者と人間関係を結んでいる登録者(以下、「第三の登録者」という)の個人情報を上記記憶手段から検索する手段と、
上記検索された第三の登録者の個人情報を第一の端末に送信する手段と、
上記第一の登録者が上記第三の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一の
メッセージを上記第一の端末から受信して上記第三の登録者の端末(以下、「第三の端末」という)に送信すると共に、第三の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき、上記記憶手段に記憶されている上記第一の登録者の個人情報と上記第三の登録者の個人情報とを関連付ける手段と、
を有してなることを特徴とする人脈関係登録サーバ。
2.裁判所の判断
まず、請求項中の文言の解釈について、以下のように述べられている。
| そもそも,特許権の効力の及ぶ範囲は特許発明の技術的範囲によって画されるものであり,特許発明の技術的範囲は,願書に添付された特許請求の範囲の記載に基づいて定められるものである(特許法70条1項)。そして,その特許請求の範囲の記載は,第三者の予測可能性や法的安定性などを確保する見地から,技術的に正確かつ簡明に記載すること,技術用語は学術用語を用いること,用語はその有する普通の意味で使用することなどが求められている(特許法施行規則24条の4,様式第29の2)。したがって,特許権の効力の及ぶ範囲の解釈は,第一義的には,特許請求の範囲の記載文言に基づいてこれを行う必要がある。 |
すなわち、まずは「特許請求の範囲の記載」に基づき文言を解釈することが適法である。また、文言の意味は「その有する普通の意味」であることが前提である。
裁判所は、「その有する普通の意味」として、以下のように、広辞苑の記載に基づく解釈を肯定した。
| 原判決が適示する広辞苑第六版(甲9),大辞林第三版(甲10),用字用語新表記辞典(乙22)及び最新法令用語の基礎知識改訂版(乙23)の各記載によれば,構成要件1D及び1Fにおける「送信したとき」の「とき」は,条件を示すものと解釈するのが日本語的に素直な解釈であるというべきであり,この点に関する原判決の認定判断に誤りがあるとは認められない。 |
なお、特許法第70条2項には「・・・明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と規定するところ、裁判所は続けて本件特許権1の明細書も考慮した。しかしながら、「送信したとき」の文言に対応する箇所は不明なため、明細書を考慮してこの文言を解釈する事ができない、と結論づけた。
第3 考察
被告サーバは、以下のような順序で処理を行う。
①会員A→サーバ (「マイミク追加リクエスト」を受信)
② サーバ→会員B(「マイミク追加リクエスト」を送信)
③ サーバ←会員B(承認を受信)
④ サーバ (会員Aと会員Bを「マイミク」として記憶)
⑤会員A←サーバ (承認された旨を送信)
本件特許権1の「送信したとき」が「条件」を示すものとされたため、本件特許権1に係る発明は、④⑤ではなく⑤④の順序で処理がなされることとなる。
請求項においてコンピュータの処理を記載する場合には、処理順序が入れ替わってもよい処理があるかどうかには留意したいところである。
また、実務上は、請求項の作成において使用する文言の意味を、辞書に掲載のとおり理解できているかにも留意したい。
(文責:三上祐子)